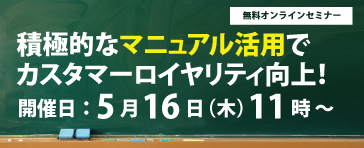マニュアルCMSとDITA対応CMSとの違い
マニュアル作成プラットフォーム「PMX」は、ドキュメントを構造化し、トピック単位に部品化して登録・管理し、再利用性を高めるとともに、インデックスの役割をするマップでドキュメント全体の構成を管理するとともに、出力内容はスタイルシートで制御します。
すなわち、基本的な考え方やアーキテクチャ自体はDITA対応CMSと同じであり、XMLデータで一元化されるという部分も同様ですが、ではマニュアル作成プラットフォーム「PMX」とDITA対応のCMSとの違いはどこにあるのでしょうか?
マニュアルCMS「PMX」とDITA対応CMSとの共通点
サイバーテックのマニュアル作成システム「PMX」もDITA(Darwin Information Typing Architecture)も、構造化ドキュメントを効率的に作成・管理・再利用するための仕組みである、という意味で共通点を持っています。また、両者ともに、複数の担当者が分業形式で、トピックというXML形式のドキュメント部品を作成、それらトピックを組み合わせて、印刷にも使えるPDF組版やHTMLによる電子マニュアルの出力など、様々な形式に再利用する制作スタイルも共通しています。
マニュアル作成システム「PMX」では、トピックやマップといったDITAが規定した構造化ドキュメントの概念を取り入れており、トピック単位でドキュメントを構造化・部品化して登録・管理し、インデックスの役割をするマップでドキュメント全体の構成を管理します。「PMX」のコンテンツ管理機能には、DITA対応CMSとよく似た、以下の機能があります。
- バージョン管理機能:「PMX」もDITAも、トピック単位やブック(マップ)単位でバージョン管理を行う事ができます。
- スタイルシートによるワンソース・マルチユース:「PMX」もDITAも、情報の内容(トピック)と情報のレイアウト(スタイルシート)を分離しており、印刷用のPDFやHTMLによる電子マニュアルの出力に関する概念も似ています。
- XML基盤:多くのDITA対応CMSは、内部にXMLを扱う事ができるDBMS(データベース・マネジメントシステム)を持ち、「PMX」同様に、編集・検索・素材管理・版管理・出力など様々な機能を有しています。
マニュアルCMS「PMX」とDITA対応CMSとの違い
では、マニュアルCMS「PMX」とDITA対応CMSを用いた場合において、求められるスキルや費用、実際のドキュメンテーションにおける違いはどのようなものでしょうか?大きく分けると以下の4点があります
DITA対応CMSよりも広い用途
DITA対応CMSは、製造業やソフトウェアの中でも、航空機や電子機器、自動車、ソフトウェアなどの大規模な技術仕様(スペック・プロセス)や技術ドキュメントをDITAドキュメント化し、その管理効率化に威力を発揮します。それだけに用途は限定され、かつ予算規模は想像を超える規模に膨らむことが一般的です。
一方、「PMX」は、格納するドキュメントはDITAに限定しません。「構造を持つ」「テキスト中心」「改訂や版管理が必要」「紙媒体と電子マニュアルの両方が必要」という要件を満たす文書全てに対応します。また、文書量も数十ページから百ページ前後の小~中規模のサービスマニュアルや保守手順書などにも対応しており、DITAライクな機能がリーズナブルに活用できるため、スモールスタートが可能です。
国産ソフトとして要望を最大限取り入れることが可能
DITA対応CMSは海外製品が多いため、お客様の要望がなかなか本国に届きにくいのが実情であり、たいてい対応が困難という回答となります。さらにDITA対応CMSは、DITA専用エディタソフトを組み合わせて使うパターンが多く、価格面でもそれなりに高価なものとなるだけではなく、サポート対応が必要となるケースが多々あります。日本語対応が可能であればまだ良いのですが、たいてい時差があるため、やりとりはスムーズに進みません。
マニュアル作成システム「PMX」は当社が開発する国産のCMSとなりますので、お客様のニーズをお聞きした上で、バージョンアップもしくはカスタマイズ対応にて、ダイレクトに製品に反映させることができます。つまり「お客様の要望をいち早く標準機能に取り込む」という、日本企業が提供するソフトウェア製品というメリットを最大限にお客様にご提供することが可能です。もちろん、海外製品によくある、日本からの撤退に伴いサポート打ち切り、もしくは英語によるサポートのみになる、といった心配もありません。
DITA 対応CMSよりも圧倒的に安いコストと短期間による立ち上げ
「PMX」は、DITA対応CMSに比べて制作や運用に関わる関係者やオペレータの教育を始めとした立ち上げ期間とコストが圧倒的に安く済みます。理由は、「PMX」がDITA自体を実現するものではなく、あくまでDITAの概念を取り入れているのみですので、DITAの難しい規約やルール・XML技術などを学習する必要がない事と、トピックやマップの編集は特別なITスキルを必要としない快適で親しみやすいインタフェースを採用した事です。
DITA対応CMSは、翻訳メモリとのシームレスな連携機能や、DITAの最新規格を取り入れることで高度でプロフェッショナルな技術ドキュメントの制作環境を提供します。それに対して「PMX」は、「Blogを書くような感覚でドキュメンテーションを効率化」というニーズに応える製品とお考え下さい。
データベース化されたコンテンツを出力する方法の違い
DITAベースの仕組みは、出力時にDITA-OT(DITA Open Toolkit)という、DITA専用のパブリッシングエンジンが必要となります。DITA-OTでは、出力するコンテンツに応じた形でスタイルシートを定義する必要がありますが、専門的な知識が必要となり、技術者によるスタイルシートの修正が必要となります。
当社が開発・販売を行うマニュアルCMS「PMX」の場合は、汎用的なスタイルシートで出力形式を調整することが可能となりますので、DITAやXMLの知識は不要です。万が一方法が分からなくなった場合であっても、当社は国内ベンダーとなりますので、全て日本語でデイタイムにサポートを行わせて頂くことが可能です。
|
御相談、ご質問はこちら |
サービスご案内資料や、特別資料「マニュアル作成の効率化とコストダウンを実現するポイントとは? 」がダウンロードできます。 |
|
最新事例の公開情報や、イベント・セミナー情報をお届けします。 |